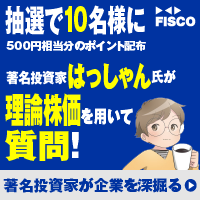暗号資産
FISCO BTC Index
8/17 1:11:46
17,373,639
カロリーベースの食料自給率に意味はあるか
2014/8/6 15:08
FISCO
*15:08JST カロリーベースの食料自給率に意味はあるか
農林水産省は5日、2013年度のカロリーベースの食料自給率が4年連続で39%になったと発表した。
食料自給率は、供給カロリーが国内生産でどのぐらい賄われているのかを示す指標。今年4月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要で、カロリー全体の約2割を占める国内産のコメの需要が増え、全体の自給率を0.2ポイント押し上げた一方、天候不順で小麦と大豆の生産量が減ったためと見られる。品目別の自給率はコメが97%、小麦が12%、大豆が23%、畜産物が16%、魚介類が64%、野菜が76%、果実が34%で、各品目に大きな変化はなかった。
また、2013年度の生産額ベースの自給率は、円安の影響で農産物の輸入額が膨らんだことから、2012年度より2ポイント低い65%で、過去最低だった2008年度と同じだった。
食料自給率は、1960年度の79%をピークに徐々に低下し、コメの凶作に見舞われた1993年度に過去最低の37%を記録。その後も高齢化や耕作放棄地の拡大など国内農業の生産基盤の弱体化などで40%前後が続いている。
カロリーベースの自給率が低迷している大きな要因の一つに、日本人の食生活の変化でカロリーの高い肉類の消費が増えていることが挙げられる。食用の家畜は約6割が国内で飼育されているが、輸入飼料で育てられるとその肉は国産とみなされないため、国産の消費が増えても自給率が下がるのだ。
政府は2020年度までに自給率を50%に引き上げる目標を掲げているが、今年度も主食のコメで消費税増税後の反動減が予想されていることや環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)などの交渉が進み安価な食品の輸入が増えれば、さらなる自給率の低下が懸念されるだけに達成はほぼ絶望的な状況となっており、今秋から目標を引き下げる議論を本格的に始める方針だ。
カロリーベースの計算法を疑問視する声も多い中、自給率の目標値を引き下げることに意味があるとは思えず、政府はこの数値を参考に生産力や調達力など農政の全体的な見直しに取り組んでいくべきだと思われる。
《YU》
関連記事

8/6 14:36
FISCO

8/6 12:31
FISCO

8/6 8:16
FISCO

8/6 8:12
FISCO

8/6 7:01
FISCO