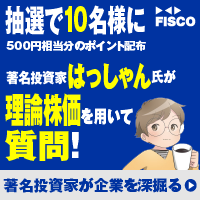暗号資産
FISCO BTC Index
1/14 19:22:10
15,105,672
円の30年を振り返る【フィスコ・コラム】
2019/4/7 9:00
FISCO
*09:00JST 円の30年を振り返る【フィスコ・コラム】
日経平均株価が過去最高値を付けたのは、平成に入って最初の年の暮れでした。円もそれに連動して水準を切り上げ、世界有数の強い通貨に成長しましたが、今や見る影もありません。改元により、平静でなかった金融市場のムードが一新されるでしょうか。
2019年のドル・円相場は波乱の年明けとなりましたが、その後は比較的穏やかな地合いが続いています。世界経済の減速が懸念されアメリカの金融政策がハト派的になるものの、4-6月期はドル売り材料が乏しく、下げはおおむね小幅にとどまると予想します。貿易取引量の加重平均や消費者物価を加味したドルの実質実効為替レート(以下、実質レート)は、ここ数年安定的に推移しています。
対照的に、私たちが日常目にするドル・円の名目レートと異なり、円の実質レートは弱まるばかりです。日銀の異次元緩和で日本株はある程度持ち直し、日本経済が復活したように見えるかもしれませんが、円の価値は過去30年間で最低レベルに落ち込んでいます。その実質レートが通貨としての円の実力を示す尺度になるとしたら、日本の国力そのものが低下していることを意味します。
ドル・円の名目レートは1985年のプラザ合意以降、(超)長期の円高傾向に振れています。一方、実質レートは阪神大震災が発生した1995年までは名目レートとほぼ連動した値動きでしたが、それをピークに下げ始め、名目レートから大きくかい離して足元の状況に至っています。日本経済がバブル崩壊後に長期間にわたりデフレに悩まされていることが、この実質レートの下落要因と考えられています。
1990年代後半に実質レートが下落方向に振れたのは、日本の災害リスクなどが意識されたほか、経済のグローバル化で東南アジアの新興国が台頭したこともその要因とみられます。新興国はその時期に通貨危機に見舞われましたが、経済成長で通貨は強くなり、相対的に円が弱含んだ可能性もあるでしょう。しかし、2000年代以降の下げは日本経済に起因するものだと専門家は指摘しています。
これから始まる日米通商協議で、アメリカのトランプ政権は実質レートの円安を問題視しています。2015年6月にドル・円が125円まで円安方向に振れた際、日銀の黒田東彦総裁は実質レートがさらに円安に振れるのは「普通に考えるとなかなかありそうにない」と述べ、ドル・円は下げ止まりました。が、日本のインフレが主要国に比べ低い状況が続くなか、実質レートが急激に上昇するとは思えません。
5月1日からの日本の元号は「令和」に決定し、世論の評価はおおむね好感を得ているようです。「平成」は「平静」の響きからほど遠く、災害や金融危機に見舞われる時代でした。ゴールデンウィーク期間中に市場が荒れるケースも時々あり、名目と実質のレートの歪(ひず)みを狙い撃ちされないとも限りません。「美しい調和」への願いが込められた新時代を占ううえで、そのつなぎ目と重なる時期の取引が注目されます。
(吉池 威)
※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。
《SK》
関連記事

4/6 19:25
FISCO

4/6 14:44
FISCO

4/6 14:41
FISCO

4/6 14:40
FISCO

4/6 14:39
FISCO