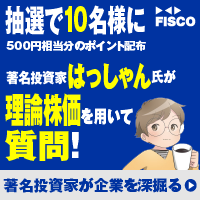暗号資産
FISCO BTC Index
1/29 17:22:35
13,489,806
米ドル買い・円売り急拡大の反動、ただ米長期金利低下は限定的
2017/7/18 11:34
FISCO
*11:34JST 米ドル買い・円売り急拡大の反動、ただ米長期金利低下は限定的
■要約
・「予想以上に鈍い米物価上昇」がきっかけになり、行き過ぎた米ドル買い・円売りが逆流。
・独長期金利上昇が続く中、米金利低下も限定的という状況が続くなら、円高も限定的か?!
■なぜ112円台へ米ドル反落したのか、これからどうなるか?
先週の米ドル/円は、週明け早々114円半ばまで一段と米ドル高・円安が進みましたが、週末には一時112円台前半まで米ドル安・円高に戻す結果となりました。なぜこうなったのか、この先はどうなるかについて、今回は考えてみたいと思います。
この間の米ドル/円は、日米長期金利(10年債利回り)差、とりわけ米長期金利と相関性の強い展開が続いてきました≪資料1参照≫。その意味では、先週米ドル反落となったのは、基本的には米長期金利が反落となった影響が大きかったでしょう。
□資料1=米ドル/円と日米10年債利回り差(2016年9月-)
出所:トムソン・ロイターより作成
米長期金利、10年債利回りは一時2.4%突破含みの動きとなったところから、週末には一時2.3%割れとなりました。トランプ政権巡る不祥事の懸念が浮上したことに加え、注目されたFRB議長の重要議会証言を受けて、「予想以上に鈍い米インフレ率上昇」が再度注目され、米長期金利低下となったとの説明が基本でした。
ただ、米10年債利回りは、金曜日に注目の米物価統計(6月消費者物価)の上昇率が予想を下回り大幅な低下となったものの、引けにかけては2.3%台を回復するなど、少なくとも先週に限っては、金利の低下も限られた状況が続いたように思われます≪資料2参照≫。ではなぜそうなったのでしょうか。
□資料2=過去一か月の米10年債利回り
出所:Bloomberg
米長期金利が6月下旬より一段の上昇に向かったのは、ECB金融緩和見直し思惑をきっかけとした独長期金利の急騰に連れた面が大きかったのでしょう。そんな独長期金利は、先週も上昇傾向が続きました≪資料3参照≫。
□資料3=過去一か月の独10年債利回り
出所:Bloomberg
以上のように見ると、独長期金利急騰をきっかけに米長期金利急騰となった動きは、独金利上昇傾向に変化がない中でも、改めて「予想以上に鈍い米インフレ率上昇」に反応し、米長期金利低下の可能性が出たため、それとの相関関係に変化のない米ドル/円も、米ドル安・円高再燃リスクが再浮上したということになるのでしょうか。
CFTC統計の投機筋の円ポジションは、先週にかけて円売り越し(米ドル買い越し)が11万枚以上に急増していました≪資料4参照≫。ちなみにこれは、2015年6月、つまり米ドル高・円安が125円でピークアウトした時以来の大幅な米ドル買い・円売りでした。かなり行き過ぎた米ドル買い・円売りになっていた可能性があったのではないでしょうか。
□資料4=CFTC統計の円ポジションと米ドル/円
出所:毎日くりっく!365
最近は、世界的な金融緩和見直しの中で、日本の出遅れが意識されたいわゆる円キャリー取引、低利の円を安く調達し、それをより高い利回りで運用する取引が拡大しているとの観測がありました。
そういった中だったからこそ、「予想以上に鈍い米インフレ率上昇」に米ドル売りという反応をしたということではないでしょうか。ただ、米長期金利の低下が、先週までのように限られるなら、それにもかかわらず米ドル売り・円買いが一段と続くか、それは微妙なのではないでしょうか。(了)
【ニュース提供・エムトレ】
《FA》
関連記事

7/18 10:50
FISCO

7/18 8:33
FISCO

7/18 8:32
FISCO

7/18 7:38
FISCO

7/17 12:20
FISCO